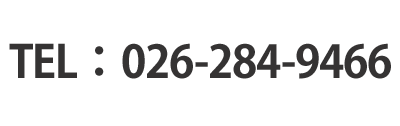
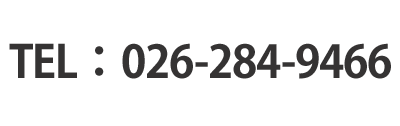
合計所得金額が2,350万円以下の個人の基礎控除額を10万円引き上げ、58万円とする(現行48万円)。
さらに、低所得者・中所得者の税負担軽減のため、合計所得金額に応じて基礎控除額が上乗せされる「基礎控除の特例」を創設。
・合計所得金額132万円以下:95万円
・合計所得金額132万円超336万円以下:88万円(2027年分以後は58万円)
・合計所得金額336万円超489万円以下:68万円(2027年分以後は58万円)
・合計所得金額489万円超655万円以下:63万円(2027年分以後は58万円)
これにより、給与収入の課税最低限は160万円となる。
※住民税の基礎控除は、大幅な減収懸念から据え置き。
| 合計所得金額 | 現行控除額 | 改正後(2027年まで) | 改正後(2027年以降) |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 | 58万円 |
| 132万円超336万円以下 | 48万円 | 88万円 | 58万円 |
| 336万円超489万円以下 | 48万円 | 68万円 | 58万円 |
| 489万円超655万円以下 | 48万円 | 63万円 | 58万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 48万円 | 58万円 | 58万円 |
給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円へ10万円引き上げ。
年齢19歳以上23歳未満の特定扶養親族等(給与収入で103万円超188万円以下)がいる場合、段階的に控除を受けられる「特定親族特別控除」を創設。
給与収入150万円以下であれば、これまでの特定扶養控除と同額の63万円の控除が受けられる。これにより、いわゆる「103万円の壁」が「150万円の壁」に実質的に引き上げられる。
| 給与収入額 | 控除額(現行) | 控除額(改正後) |
|---|---|---|
| 103万円以下 | 63万円 | 63万円 |
| 150万円以下 | 0円 | 63万円 |
| 188万円以下 | 0円 | 減額控除あり |
・18歳以下の扶養親族を有する世帯または夫婦いずれかが39歳以下の世帯(「子育て世帯等」)に対し、住宅ローン控除の借入限度額を上乗せ。
※2025改正部分 借入限度額 【新築住宅・買取再販住宅】の子育て世帯
長期優良住宅・低酸素住宅 4,500万円 → 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 → 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000面円 → 4,000万円
・子育て世帯等で合計所得金額1,000万円以下の場合、新築住宅の床面積要件を40㎡に緩和(通常50㎡以上)。
子育て世帯等が一定の「子育て対応改修工事」を行った場合、工事費用の10%を所得税から控除。対象工事限度額250万円、最大25万円控除。
※〈 特別控除額 〉
標準的な工事費用相当額(限度額250万円)×10 (最大25万円控除)
23歳未満の扶養親族を有する居住者に対し、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の適用限度額に2万円を上乗せし、最大6万円の控除を可能に。
※控除総額の上限(12万円)は据え置きのため、介護医療・年金控除との兼ね合いにも要注意です。
・対象となる費用に「乳児等通園支援事業」に係る費用を追加。
・適用期限を2027年3月31日まで2年間延長。
老後資産形成を促進するため、確定拠出年金の月あたりの拠出限度額等を引き上げ。
・適用対象となる合計所得金額の要件を「500万円以下」から「1,000万円以下」に2026年分から緩和。
・控除額を所得税35万円→38万円(2026年分~)、住民税30万円→33万円(2027年分~)に引き上げ。

令和7年から、子育て世帯や若者夫婦を応援する税制改正が始まります。住宅ローン控除やリフォーム減税などが期間限定で拡充され、家計の負担を軽減します。ご自身が対象になるか、この機会にぜひご確認ください。
・課税標準法人税額(課税標準)に対し、税率4%の新たな付加税を創設。
・課税標準法人税額は基準法人税額から500万円(基礎控除額)を控除した金額。
・中小企業者等に対する法人税の軽減税率(所得のうち年800万円以下の部分に対する税率15%)の適用期限を延長。
・ただし、所得が年10億円を超える事業年度については、800万円以下の部分に適用される税率が17%に引き上げ。
・グループ通算制度を適用している法人は特例税率の対象から除外。
新リース会計基準(借手のオンバランス処理)に対応するため、リース税制の取扱いが見直されました。これにより、会計と税務の差異を調整しつつ、従来どおり税務上は「賃貸借処理」を基本とする扱いが維持されています。

令和7年から、子育て世帯や若者夫婦を応援する税制改正が始まります。住宅ローン控除やリフォーム減税などが期間限定で拡充され、家計の負担を軽減します。ご自身が対象になるか、この機会にぜひご確認ください。
| カテゴリー | 制度名 | 内容のポイント | 目的 |
|---|---|---|---|
| 住宅ローン控除 | 子育て世帯等¹ | ローン借入限度額の上乗せ コンパクトな新築住宅も対象に(床面積40㎡~) |
令和7年 (2025年)限定 |
| 住宅リフォーム税制 | 子育て世帯等¹ | 「子育て対応改修」で最大25万円の税額控除 | 令和7年 (2025年)限定 |
| 生命保険料控除 | 23歳未満の扶養親族がいる方 | 控除の限度額が4万円→6万円にアップ | 令和8年 (2026年)限定 |
| ¹「子育て世帯等」とは:18歳以下の扶養親族がいる、または夫婦のどちらかが39歳以下の世帯 | |||
対象:
18歳以下の扶養親族を有する世帯、または夫婦のいずれかが39歳以下の世帯(「子育て世帯等」と定義)。
改正内容:
・借入限度額の上乗せ: 子育て世帯等に対して、住宅ローン控除の借入限度額が上乗せされます。これにより、より多額のローンを組んでも控除の恩恵を受けやすくなります。
・新築住宅の床面積要件の緩和: 合計所得金額1,000万円以下の「子育て世帯等」に限り、新築住宅の床面積要件が40㎡に緩和されます(通常は50㎡以上)。これにより、よりコンパクトな住宅でも控除を受けられるようになります。
目的:
急激な住宅価格の上昇や子育て世帯の住居費負担の軽減を支援。
注意点:
この措置は令和7年(2025年)限りの時限措置とされています。
対象:
住宅ローン控除と同様の「子育て世帯等」。
改正内容:
既存住宅について一定の「子育て対応改修工事」を行った場合、その工事費用の相当額の10%が所得税から控除されます。
対象工事限度額は250万円で、最大25万円の控除が受けられます。
目的:
子育てしやすい住環境へのリフォームを促進し、子育て世帯の住居環境改善を支援。
注意点:
この措置も令和7年(2025年)限りの時限措置です。
対象:
23歳未満の扶養親族を有する居住者。
改正内容:
新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、現行の4万円の適用限度額に対して2万円が上乗せされ、最大6万円の控除が受けられるようになります。
目的:
子育て世帯の経済的負担軽減の一環として、生命保険を活用した将来への備えを支援。
注意点:
この措置は令和8年(2026年)限りの時限措置とされています。
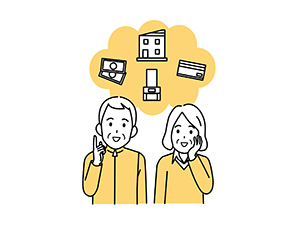
令和7年度税制改正において、相続不動産に直接関わる税制上の大きな改定として、以下の点が決定・成立しています。これらの多くは、2025年4月1日から施行されています。
ただし、相続不動産に関する重要な法改正は、税制改正とは別に民法や不動産登記法などでも近年行われており、これらの影響も令和7年以降に本格化しますので、合わせて解説します。
令和7年度税制改正(税制上の改定)
| 合計所得金額 | 現行控除額 | 改正後(2027年まで) | 改正後(2027年以降) |
|---|---|---|---|
| 税制改正 (2025/4/1~) |
相続税の物納制度の見直し | 高齢の相続人ほど、物納が認められやすくなる可能性 | 納税負担の軽減 |
| 登録免許税の免税措置延長 | 相続登記の際の税金の免除期間が2027/3/31まで延長 | 相続登記の促進 | |
| 生物多様性維持協定地の評価明確化 | 対象の土地の相続税評価額が20%減額される | 環境保全活動の支援 | |
| 法改正 (施行済み) |
相続登記の義務化 | 相続を知ってから3年以内の登記が義務(違反すると過料も) | 所有者不明土地問題の解消 |
| 相続土地国庫帰属制度 | 一定の要件を満たした不要な土地を国に引き渡せる | 所有者不明土地の発生抑制 |
改正内容:
相続税を金銭で納付することが困難な場合に、相続財産(不動産を含む)で納税できる「物納」制度について、物納を許可する限度額の計算方法が見直されました。
具体的には、物納許可限度額の計算の基礎となる延納年数の上限が、「納期限等における申請者の平均余命の年数」となります。
これにより、従来の最長20年の延納期間計算に比べて、申請者の年齢によっては延納可能額が少なくなり、物納が認められやすくなるケースが増える可能性があります。
目的:
高齢化が進む中で、相続人が高齢であるケースが増え、相続財産に占める不動産の割合が高い場合の納税負担を軽減し、物納制度をより利用しやすくするため。
適用時期:
2025年4月1日から適用。
改正内容:
相続によって土地を取得し、一定の要件を満たす場合に、その登録免許税を免除する措置の適用期限が2年間延長され、2027年3月31日までとなりました。
目的:
相続登記の促進を図るため。特に相続登記の義務化に伴い、未登記の解消を後押しする狙いがあります。
適用時期:
2025年4月1日から適用。
改正内容:
「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」に規定する生物多様性維持協定が締結された一定の土地について、相続税・贈与税の評価額から、その土地の評価額に20%を乗じた金額を控除して評価することが明確化されました。
目的:
生物多様性の保全活動への貢献を税制面から支援するため。
適用時期: 2025年4月1日から適用。
近年施行された相続不動産に関する重要な法改正(税制改正ではないが関連性が高い)
以下の改正は、相続不動産の取り扱いに大きな影響を与えるため、合わせて確認が必要です。
内容:
不動産を相続により取得した相続人は、自己のために相続があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請することが義務付けられました。
罰則:
正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象となります。
・過去の相続も対象: 2024年4月1日以前に相続が発生していた不動産も義務化の対象で、その場合は「施行日(2024年4月1日)または相続で取得したことを知った日のいずれか遅い日から3年以内」が期限となります(最長で2027年3月31日まで)。
目的:
所有者不明土地問題の解消。
影響:
相続発生後の不動産の管理や、その帰属を早期に確定することが求められるため、相続放棄の判断なども迅速に行う必要性が高まります。
内容:
相続または遺贈により土地を取得した者が、一定の要件を満たした場合に、その土地を国に引き渡すことができる制度です。
要件と負担金:
建物がないこと、担保権などが設定されていないこと、管理に過大な費用がかからないことなどの要件があり、国への帰属が承認された場合には、10年分の土地管理費相当額の負担金(原則20万円)を納付する必要があります。
目的:
不要な土地の相続を避けたい場合の選択肢を提供し、所有者不明土地の発生を抑制するため。
影響:
相続放棄を検討する際、負債がない不要な土地であれば、この制度を利用することで相続放棄せずに済む可能性があります。
これらの改正は、相続不動産の管理や納税、そして所有者不明土地問題の解決に向けた国の取り組みの一環として、相互に関連し合っています。相続不動産をお持ちの方や相続を控えている方は、これらの変更点を正確に理解し、適切な対応をとることが重要です。

現在の時点(2025年5月29日)において、令和7年度税制改正で空き家管理に直接関わる税制上の大きな改定が国会で決定・成立したという情報はありません。
しかし、空き家対策に関する法改正や制度運用は近年活発化しており、令和7年以降もその影響が継続したり、本格的に施行されたりするものがあります。 これらは税制改正とは直接関係ないものの、空き家の管理や活用に大きな影響を与えるため、関連事項として解説します。
I. 近年施行された空き家対策に関する重要な法改正・制度運用(税制改正ではないが関連性が高い)
以下の多くは、2023年12月13日に施行された改正空家等対策の推進に関する特別措置法の影響です。
改正内容:
これまでの「特定空き家等」(倒壊の危険性などがある空き家)に加えて、新たに「管理不全空き家」という区分が新設されました。これは、放置すれば「特定空き家等」になるおそれのある空き家を指します。
影響:
・行政による指導・勧告の強化: 「管理不全空き家」に対しても、市町村が助言、指導、勧告を行うことができるようになり、早期に管理不全の状態を改善するよう促されることになります。
・勧告による固定資産税等の軽減措置解除の可能性: 「特定空き家等」に指定されて勧告を受けた場合、固定資産税の住宅用地特例(固定資産税・都市計画税が最大6分の1に軽減される措置)が解除され、税負担が増加する可能性があります。 「管理不全空き家」についても、市町村が勧告を行った場合、自治体の判断によっては同様に固定資産税の軽減措置が解除される可能性があります。
施行時期:
2023年12月13日施行済み。
改正内容:
市町村が、空き家の活用を重点的に促進する区域を「空き家等活用促進区域」として指定できるようになりました。
影響:
この区域内では、用途変更や増改築がしやすくなるなど、建築基準法の規制が一部緩和される可能性があり、空き家の利活用が促進されることが期待されます。
改正内容:
所有者不明土地・建物の問題に対処するため、改正民法や不動産登記法が施行されています。特に、相続登記の義務化(2024年4月1日施行)や、相続土地国庫帰属制度(2023年4月27日施行)は、空き家が相続によって発生した場合の所有権の明確化や、不要な土地の国庫帰属を促進し、空き家の管理問題の間接的な解決に繋がります。
影響:
空き家の所有権が不明確なことで管理が放置される事態を抑制し、管理責任の所在を明確にする。
II. 空き家管理に関連する税制優遇(既存制度の継続・見直し)
令和7年度税制改正で、空き家管理に直接紐づく新たな税制優遇が創設されたわけではありませんが、既存の税制優遇が継続・一部見直しされています。
内容:
相続により空き家となった特定の要件を満たす居住用家屋(とその敷地)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
適用期限:
令和7年(2025年)12月31日までの譲渡に適用されます。 (今回の税制改正で延長されました)
改正点(令和6年度改正で適用済み):
・譲渡者の要件が「相続開始直前まで被相続人が居住していた」から、「相続開始直前まで被相続人が居住していた家屋を売却する」場合に、相続人がその家屋に居住していなくても適用されるように緩和されました。
・相続開始から売却までの期間が「3年を経過する日の属する年の12月31日まで」とされていましたが、「3年を経過する日」を上限に拡大(例:2024年4月1日相続開始なら2027年3月31日までが対象)。
・耐震基準を満たさない家屋を解体して売却する場合の敷地に係る控除要件が緩和されました。
影響:
空き家を円滑に流通させるための重要な税制優遇であり、管理されていない空き家を減らすことにも寄与します。
まとめ
令和7年度税制改正では、空き家管理そのものに関する税制上の大きな「改定」はありませんでしたが、近年施行された改正空家等対策の推進に関する特別措置法や民法・不動産登記法改正が、空き家の管理や所有者の責任に大きな影響を与えています。
特に、「管理不全空き家」の新設や固定資産税の軽減措置解除の可能性は、空き家所有者にとって喫緊の課題となる可能性があります。一方で、空き家特例の延長は、空き家を売却・処分する際の重要な支援策として引き続き活用できます。
空き家所有者は、これらの法改正や制度の運用変更を把握し、自身の空き家の状況に応じて適切な管理や対策を検討する必要があります。
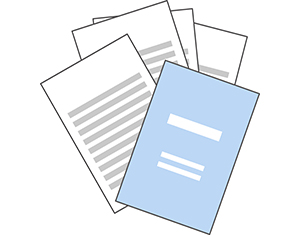
2024年から2025年にかけて、不動産登記や必要書類について、いくつかの重要な改定が行われています。主なポイントは以下の通りです。
義務化の背景:
所有者不明土地問題の解消を目的としています。
内容:
相続により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする義務が課せられました。
罰則:
正当な理由なくこの義務を怠った場合、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。
・過去の相続にも適用:法改正以前に発生した相続についても義務化の対象となります。
添付書類:
基本的には従来の相続登記に必要な書類(被相続人の戸籍謄本一式、住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書、遺産分割協議書または遺言書、固定資産評価証明書など)が必要です。
義務化の背景:
相続登記の義務化と同様に、所有者不明土地問題の解消を目的としています。
内容:
不動産の登記名義人は、氏名や住所に変更があった場合、変更日から2年以内に変更登記の申請を行う義務が課せられます。
罰則:
正当な理由なくこの義務を怠った場合、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
・職権による変更登記制度: 登記名義人の負担軽減のため、登記官が住基ネット情報を利用して職権で変更登記を行う仕組みも導入されます。この場合、本人の費用負担はありません。
内容:
2025年4月21日以降に所有権の保存・移転等の登記を申請する場合、申請書に所有者の氏名、住所に加え、氏名のフリガナ、生年月日、メールアドレスなどを併せて記載し、申出をする必要があります(「検索用情報」の提供)。
既存の不動産所有者:
2025年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である方も、別途ウェブ上などで検索用情報を提供できるようになる予定です。これにより、将来の住所変更登記の義務化に備えることができます。
目的:
登記官が登記名義人の情報をより正確に把握し、将来的な住所・氏名変更登記の職権化に繋げることを目的としています。
内容:
外国人個人が所有者となる不動産登記上の氏名について、カタカナや漢字の日本語での氏名の登記のほか、ローマ字表記を併記できるようになりました。
国内連絡先の登録:
外国に居住する登記名義人については、国内連絡先の登録が必要となる場合があります。国内連絡先を登録するには、承諾書と印鑑証明書などが必要です。
